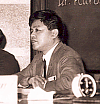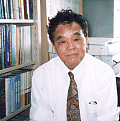 国立遺伝学研究所に黒田行昭先生をお訪ねしました。日本組織培養学会の初期には、毎年英文の研究業績集を出版していました。これは会員が学術雑誌に発表し
た研究業績に内容抄録をつけたものと、学会発表のリストを収録したもので、随分労力がかかり神経を使うお仕事でした。初めの7年間は山田正篤先生、その後
の8年間を黒田先生が編集なさっていました。御自身たくさんの業績を残されながらの、その丹念な事務能力には会員の誰もが敬服していたと思います。遺伝研
を定年になられてから、麻布大学環境保健学部生命科学講座を担当され、今は遺伝研で名誉教授として研究を続けておられます。その上、今も複数の大学や研究
機関で後輩の教育や研究の顧問としてお忙しそうでした。
国立遺伝学研究所に黒田行昭先生をお訪ねしました。日本組織培養学会の初期には、毎年英文の研究業績集を出版していました。これは会員が学術雑誌に発表し
た研究業績に内容抄録をつけたものと、学会発表のリストを収録したもので、随分労力がかかり神経を使うお仕事でした。初めの7年間は山田正篤先生、その後
の8年間を黒田先生が編集なさっていました。御自身たくさんの業績を残されながらの、その丹念な事務能力には会員の誰もが敬服していたと思います。遺伝研
を定年になられてから、麻布大学環境保健学部生命科学講座を担当され、今は遺伝研で名誉教授として研究を続けておられます。その上、今も複数の大学や研究
機関で後輩の教育や研究の顧問としてお忙しそうでした。
- 「先生が組織培養を使おうと思われたころのことをお話しください」
「僕はね京大理学部の出身なんですよ。卒論はショウジョウバエの発生についてでね、卒業してから何とかしてショウジョウバエの分化を試験管内で観察した かったのですね。そして幸運にも阪大医学部に新設された遺伝学教室の助手に採用されましてね、早速ショウジョウバエの培養に取り掛かりました」
- 「お師匠さんは・・」
「その頃、日本で昆虫の培養している人なんてあまりいませんでしたね。だから試行錯誤の繰り返しでしたよ。とにかく技法の成書もありませんでした。問題は 材料をどうやって無菌にするか、そしてどんな培養液を使うか、から始めました。材料を無菌にするのには苦労しましたよ。大体、次亜塩素酸を使って幼虫を消 毒するのですから、次亜塩素酸の濃度が薄ければ雑菌が生えるし、濃過ぎると幼虫が死んでしまうし。毎日々々失敗の連続でした。その内に無菌的に蠅を飼うこ とを思いついて、今の無菌動物飼育ですね、それからは仕事がはかどりました。卵と餌を滅菌して、無菌的な幼虫にするわけです。ショウジョウバエでは幼虫か ら蛹になった時、ドラマチックに変態してほとんどの幼虫組織は融解してなくなり、成虫原基からできるのですが、複眼や翅の原基を使って培養内でその分化が 確かめられました。
培養液も大変でしたね。今でも使われているグレイスの培養液の処方が発表されたころでした。基本的にはそれぞれの昆虫の体液の組成を参考にして、基礎塩 類溶液を処方するのですが、ショウジョウバエでは小さくて体液が集められない、それでカイコの体液組成を参考にしました。日本ではカイコの生理や生化学的 な研究は進んでいましたから」
- 「哺乳動物の培養液は参考にならなかったのですか」
「今では常識でしょうが、昆虫ではナトリウムは少なくてカリウムが多い。糖はトレハロースですし、アミノ酸は哺乳動物の50倍ですから、昆虫用として処方 しなくてはなりませんでした。でもヒントはありましたよ。その頃、勝田さんが鶏胎児抽出液の中の成長促進物質は核酸だという論文を出されましたね」
- 「そうでした。あのころワトソン・クリックのDNAで沸いていましたね。それで勝田先生も伝染病研究所の西岡久壽弥先生と相談
して鶏胎児抽出液から核酸を抽出したのでした。ペントース核酸PNAと言っていたころでした。始めはこれこそ成長促進物質だと思われた結果を得ましたが、
結局、核酸まで精製すると効果がなくなってしまい、分画としてはタンパク質までが有効だというところまでで終わりました。いろいろと培養法が進歩して、鶏
胎児抽出液そのものが、培養液の成分として使われなくなってしまいましたものね」
「それからイーストエキスやカゼイン水解物を使ったのも哺乳動物培養を参考にしました」
- 「その後、先生は哺乳動物細胞を使う実験に切り替えられましたね」
「そう、動物細胞でミュータントを取って、代謝やDNA合成を調べることで、遺伝的な研究をしようと思ったのです。初めは L や HeLa を使っていましたが、1957年にモスコーナの論文に出会って、非常に興味を持ちました。モスコーナの論文は細胞を浮遊状態で旋回培養することで、もとの 組織に近い構築をもった細胞集塊を作らせることができるというものでした。細胞培養では分化の問題を扱うのは困難です。それが旋回培養では、例えば肝臓か らの細胞浮遊液と腎臓からの細胞浮遊液とを混合して培養すると、肝臓と腎臓それぞれの細胞は細胞選別現象を起こしてそれぞれ同種細胞どうしが接着して、そ れぞれの組織をもった細胞集塊ができるというのですから、これを使えば試験管内での分化を調べられると思いました。そこで早速、シカゴのモスコーナの所へ 留学の手続きを取りました。幸に、奨学金が貰えることになって、1年留学しました。
モスコーナの所では鶏胎児の軟骨の分化がテーマでした。モスコーナは単層培養はやっていませんでした。そこで、私が初代培養を単層で培養してから旋回培養 に移してみました。すると初代の単層培養の期間が長くなるほど、旋回培養での軟骨組織再構成能力が低下するのです。そのとき軟骨細胞らしい細胞が減って、 繊維芽細胞様の細胞が増えています。その組織構築を作らなくなった鶏軟骨細胞浮遊液に、マウスの軟骨初代培養を混ぜて旋回培養をすると、今度は組織構築を もった細胞集塊がちゃんとできるんですよ。それを染色して調べてみると、鶏とマウス両方の細胞が入り交じってキメラ状の軟骨組織ができていたのです」
- 「その時、鶏の繊維芽細胞はどうなっていたのですか」
「見事に軟骨に分化していました。この細胞集塊を作る能力は蛋白合成阻害剤やDNA合成阻害剤で阻害されます」
- 「旋回培養は一時よく使われましたね。私たちも腫瘍性の指標に使ったことがあります。正常細胞よりも腫瘍細胞の方が、大きな細胞集塊をつくりましたから。何だか昔の方が色色な培養法を使っていたようですね」
「技術は進歩しましたし、便利になったけれど、一人々々の研究者としては培養液のアミノ酸を自分で量らなくても粉末が買えるから培養液の組成についての知 識が低くなっているし、血清をどうやって分離するかも知らないし、局面しかわからない若者が増えましたね。せめてもっと本をよく読んで基本的な知識を身に つけて欲しいですね」
- 「そうですね。先生が書かれた〈動物組織培養法・モダンバイオロジーシリーズ23・共立出版株式会社・1974〉をきちんと読めば組織培養の基礎はわかるはずですもの」
「あのシリーズは今絶版になっています」
−田島先生がお見えになりました−と声がして、蚕の研究で有名な田島先生が入って来られました.この日、遺伝研究所での大切な会議が開かれると伺っていましたが、その会議前の時間をさいて私の取材に応じて下さったのでした.
- 黒田先生の「動物組織培養法」による「株」の定義が、我が国で出版された書籍の中では最も正確なものの一つであると思われます.山田先生の解説ともほぼ一致しております.但し、本書では細胞培養を「組織培養」と記述しております.
山田先生は、細胞の培養については組織培養と記述しないほうが良いのではないかという見解をお持ちです.